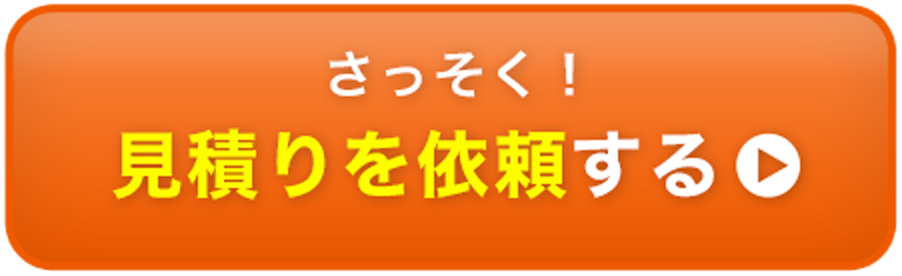所得の種類とは?
所得の種類は10種類あり、所得の種類によって課税方式も違ってきます。
所得の種類一覧
所得の種類は、「どのように、その所得を得たか」「どのように、稼いだか」といった事情によって、以下に区分されます。
| 種類 | 概要 | 課税方法 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 商工業や漁業、農業などの自営業から生ずる所得 ※個人事業主やフリーランスなど | 総合 |
| 事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 | 申告分離 | |
| 不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 ※アパートの家賃収入など | 総合 |
| 利子所得 | 国外で支払われる預金等の利子などの所得 | 総合 |
| 特定公社債の利子などの所得 | 申告分離 | |
| 預貯金の利子などの所得 | 源泉分離 | |
| 配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得 ※上場株式等の配当等について、申告分離課税を選択(注)したものを除く。 | 総合 |
| 上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択(注)したものの所得 | 申告分離 | |
| 特定目的信託(私募のものに限る。)の社債的受益権の収益の分配などの所得 | 源泉分離 | |
| 給与所得 | 会社員が勤務先から受ける給料、パートアルバイト収入、賃金、役員報酬、賞与、歳費などの所得 | 総合 |
| 雑所得(公的年金等) | 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給、一定の外国年金などの所得 | 総合 |
| 雑所得(業務) | 原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得 | 総合 |
| 雑所得(その他) | 生命保険の年金、暗号資産取引による所得など他の所得に当てはまらない所得 | 総合 |
| 先物取引に係る所得 | 申告分離 | |
| 譲渡所得 | ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 | 総合 |
| 土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得 ※株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く。 | 申告分離 | |
| 一時所得 | 生命保険の満期保険金や一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 | 総合 |
| 保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など | 源泉分離 | |
| 山林所得 | 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 ※5年以内に譲渡した場合には、事業所得か雑所得 | 申告分離 |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 | 申告分離 |
出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_03.htm
また、所得のなかには非課税となるものもあり、以下が例示になります。
| 所得 | 具体例 |
|---|---|
| 利子・配当所得関連 | ・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る配当 ・納税準備預金の利子 ・オープン型証券投資信託の特別分配金 ・勤労者第三形成型年金(住宅)貯金の利子 |
| 給与所得・公的年金関連 | ・傷病年金や遺族年金 ・限度額内の通勤手当や業務上必要な現物給与 ・国外勤務する人が受ける一定の在外手当 ・特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益(いわゆる「税制適格ストック・オプション」) ・文化功労者年金法の規定による年金 |
| 譲渡所得・山林所得関連 | ・生活に必要な動産の譲渡による所得 ・NISAやジュニアNISAなどの少額投資非課税制度に係る譲渡所得 ・国や地方公共団体等に財産を寄附した場合の譲渡所得など |
| その他 | ・学資金と扶養義務の履行のために受け取る金品 ・国または地方公共団体が提供する保育・子育て助成事業により給付される金品 ・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの ・心身に加えられた損害、または突発的な事故により資産に加えられた損害に対して得る保険金や損害賠償金、慰謝料 ・公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し取得する金銭 ・都道府県や市区町村から支払われる一定の給付金 |
所得の個別解説
①事業所得
事業所得とは商工業や漁業、農業などの自営業から生ずる所得で個人事業主やフリーランスの収入がこれにあたります。
事業所得=収入金額-必要経費
1月1日から12月31日までに得た収入から必要経費を差し引いた金額です。
②不動産所得
不動産所得とは、土地、建物などの不動産の賃貸による所得です。他にも、地上権などの不動産に設定されている権利を貸し付けて得る収入や、船舶や航空機を貸し付けて得る収入も、不動産所得となります。不動産所得は、1年間に得た家賃や更新料などの総収入金額から、必要経費を差し引いて計算します。
不動産所得=総収入金額-必要経費(修繕費、減価償却費、損害保険料など)
共益費として受け取っている電気代や光熱費などがある場合には、これらを総収入金額に含めます。一方、将来的に返還する敷金や保証金は、原則として収入には含めませんが、契約上返還の必要がなくなった場合には、返還の必要がなくなった日の属する年の収入に含めます。
③利子所得
公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。利子所得には必要経費はありません。収入がそのまま所得になります。なお利子所得は、所得税15%・住民税5%が源泉徴収(源泉分離課税という)されます。
※日本国外の銀行の利子等、所得割(総合課税)の対象になるものもあります。
④配当所得
配当所得=配当収入-借入金の利子※
株式会社などの法人から受ける剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配などによる所得を配当所得といいます。株式の配当金や投資信託の分配金は、「配当所得」として、上場株で通常税率15.315%、未上場株で20.42%が源泉徴収されています。
※借入金の利子とは、株式等を取得するために借り入れた負債の利子のことです。
⑤給与所得
給与所得=給与収入-給与所得控除
勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与など(パート・アルバイトによる収入も含む)を給与収入といい、そこから給与所得控除額を差し引いた金額を給与所得といいます。役員報酬や青色事業専従者の給与も含まれます。
給与収入から給与所得を計算する場合は、次の表を使います。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
⑥雑所得
公的年金や年金払いの保険金など、他の所得のいずれにも当たらない所得のことです。非営業用貸金の利子、著述家、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、Uber-Eatsの配達料なども雑所得に該当します。
雑所得は、必要経費を除いて20万円超の場合には、確定申告が必要です。
雑所得(公的・退職年金) = 年金収入-公的年金等控除
雑所得(その他)= 収入金額-必要経費
⑦譲渡所得
・土地建物等以外【総合課税】
譲渡所得=譲渡収入-必要経費-特別控除(50万円)
・土地建物等【分離課税】
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
・株式等譲渡所得【分離課税】
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用+負債利子)
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生ずる所得を譲渡所得といいます。株式等を除く土地建物等・その他の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。
(1)土地建物等及び株式等の譲渡については、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算する「分離課税」により課税されます。源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益等については、源泉徴収されます。
(2)総合課税の長期譲渡所得については、上記の式で出した譲渡所得の金額を1/2したものが課税対象額となります。
⑧一時所得
一時所得=一時収入-必要経費-特別控除(50万円)
上記の式で算出した一時所得の金額を1/2したものが、課税対象額となります。生命保険の満期保険金、懸賞当選金品、競馬などの払戻金など、一時的に生ずる所得を一時所得といいます。一時所得には、50万円の特別控除が認められていますので、必要経費となる払込保険料などを差し引いて50万円以下であれば、税金はかかりません。
また、勤務先で年末調整をしてもらえるサラリーマンなどは、一時所得の合計額の2分の1が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
⑨山林所得
山林所得=山林収入-必要経費-特別控除(50万円限度)
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することにより生ずる所得を山林所得といいます。ただし、山林を所得してから5年以内に譲渡した場合には、事業所得か雑所得となります。
⑩退職所得
退職所得=(退職収入-退職所得控除)×1/2
退職により勤務先から受ける退職手当などの所得を退職所得といいます。通常は所得税と住民税について源泉徴収して支払われているので、確定申告は必要ありません。
また、勤続年数が5年以下の場合は、「特定役員退職手当等」または「短期退職手当等」に該当し、一定額について「2分の1課税」が適用されない等の調整が入ります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 2年以下 | 80万円 |
| 3年~20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
まとめ
所得の種類によって計算方法がそれぞれ分かれているため、ご自身の収入が一体どれに該当するのかをきちんと確認する必要があります。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、確定申告の手続きを丸投げでお受けするプランもございますので、ご自身での手続きに不安のある方はぜひお問い合わせください。