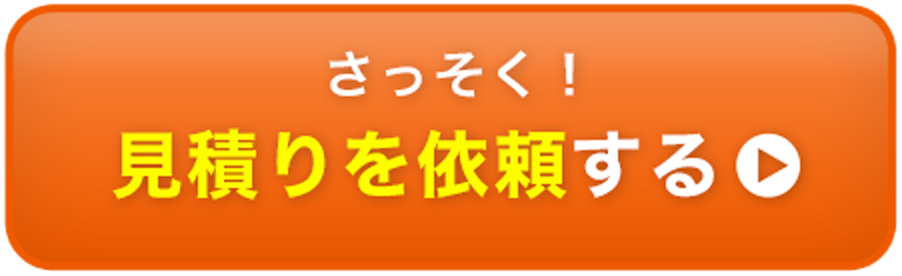所得計算において重要性が高い「減価償却」とは?

不動産所得の計算において重要性が高い「減価償却」がどのようなものか、具体的な計算方法を交えて解説していきます。
減価償却とは
何年にもわたって使う高額なものを購入したとき、買った年に費用として一括計上するのではなく、耐用年数に応じて費用化することを「減価償却」といいます。
上記の例の場合、1年間に10万円ずつ、10年間にわたって費用計上していきます。この計上された費用のことを「減価償却費」といいます。
減価償却の耐用年数とは
減価償却の対象となる資産の取得価格をどれくらいの年数にわけて計上すべきか、品目ごとに定められています。
耐用年数は資産の種類によって細かく定められており、例えば鉄骨鉄筋コンクリート造の建物であっても、用途やその他条件によって耐用年数が異なります。
<資産ごとの耐用年数:国税庁>
減価償却の目的
何年も使える固定資産を購入した際に、一括で経費として計上すると、その年の経費が膨大になり、赤字になってしまう可能性が高くなります。また翌年からは固定資産から経費が発生しないようになり、結果として利益と経費の金額が不正確になってしまいます。
そのため、耐用年数に応じて減価償却を行うことで、経営の実態に合った経費を計上することとしています。
減価償却の対象になる資産とならない資産
減価償却の対象になる資産
減価償却の対象にならない資産
減価償却の償却方法
減価償却の償却方法には定額法と定率法があります。
定額法の償却方法
定額法で耐用年数6年の場合、償却率は0.167となりますので、次の式で計算します。
1,200,000×0.167=200,400円
仕事とプライベートで半々で使用しているので、経費は上記の半分だけ計上できることになります。この車の場合は、200,400円×1/2=100,200円が1年間の減価償却費となります。
また資産を新たに買った年には、使った期間で按分しなくてはいけません。7月に購入しているので、実際に経費にできるのは12分の6の金額となります。
100,200×6/12月=50,100円
【定額法による償却額】
車を買った年の減価償却費:50,100円
2年目の減価償却費:100,200円
定率法の償却方法
定率法で耐用年数6年の場合、償却率は0.333となりますので、次の式で計算します。
1,200,000×0.333=399,600円
定額法と同様、仕事とプライベートで半々で使用しているので、経費は半分だけ計上できます。この車の場合は、399,600円×1/2=199,800円が減価償却費となります。
また7月に購入しているので、実際に経費にできるのは12分の6の金額となります。
19万9,800円×6/12=9万9,900円
2年目は、車の未償却残高:800,400円(取得価額:1,200,000-前年までの減価償却累計額:399,600)に償却率を乗じていきます。
800,400円×0.333=266,533円
仕事とプライベートで半々で使用しているので、経費は上記の半分だけ計上できることになります。
【定額法による償却額】
車を買った年の減価償却費:99,900円
2年目の減価償却費:133,266円
定額法と定率法の違うところ
定額法はその資産の「取得価額」に償却率を乗じるのに対して、定率法はその資産の「未償却残高」に償却率を乗じるという点です。「未償却残高」とは、その資産から前年以前に減価償却された金額を差し引いた価格のことです。未償却残高は年を経るごとに減っていきます。
定額法の特徴
耐用年数に応じて毎年同じ額だけの減価償却費を計上していきます。計算式が簡潔で直感的に理解しやすいという特徴もあります。
定率法の特徴
最初のうちは減価償却の額が多く、年を経るごとに減価償却費がだんだん少なくなっていく特徴があります。したがって、購入初期に減価償却を計上したい場合は定率法を選ぶべきとなります。定額法にするか定率法にするかは、事業者が自分で選択することができます。
定率法を選択したい場合は、申告期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。届出を出さなかった場合は自動的に定額法になります。
まとめ
減価償却とは何年にもわたって使う高額なものを購入したとき、買った年に費用として、一括計上するのではなく、耐用年数に応じて1年ずつ分割して経費計上することです。
ただし、減価償却の対象となる資産は時がたつにつれて価値が下がっていく資産であり、すべてを減価償却できるわけではありません。
償却方法には主に定額法と定率法があり、定額法にするか定率法にするかは、事業者が自分で選択することができます(不動産の場合は定額法のみ)。ただし、定率法を選択したい場合は、申告前までに税務署に届出書を出さなくてはいけません。届出を出さなかった場合は自動的に定額法になります。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、減価償却計算も含めて確定申告の手続きを丸投げでお受けするプランもございますので、ご自身での手続きに不安のある方はぜひお問い合わせください。