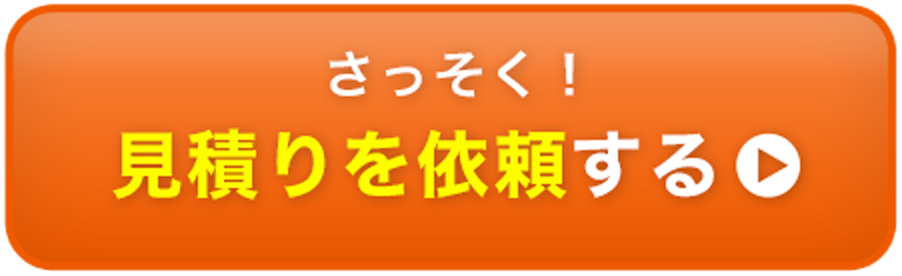ふるさと納税とは? 申請方法や限度額の把握方法を紹介

ふるさと納税とは
自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、控除限度額の範囲内であれば、寄付額のうち2,000円を超える部分の金額が、所得税と住民税から控除される制度です。控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った年分の確定申告を行う必要があります(ワンストップ特例制度を利用する場合は不要です)。
また、寄付先の自治体からお礼の品として「寄付金額の最大3割の返礼品」をもらうことができ、返礼品には各地の特産品や日用品・家具・家電・宿泊券など、様々な種類があります。
控除限度額の計算方法
ふるさと納税の控除限度額は「所得税からの控除額+住民税からの控除額」で計算できます。なお、所得税からの控除額と住民税からの控除額は、それぞれ下記の計算式により求めます。
所得税からの控除額
住民税からの控除額
メリット・デメリット
メリット
- 被災地の復旧、復興に協力できる
- 税金の前払いで好きな返礼品がもらえる
- 自身の故郷など好きな自治体に納税できる
- クレジットカードで決済すれば、クレジットカードのポイントがたまる
- ふるさと納税サイトでもポイント還元される(令和7年10月廃止予定)
デメリット
- 税額控除を受けるためには確定申告、または一定の申請に手間がかかる
- 控除限度額の計算方法が複雑で、最適な寄付の金額を把握するのが難しい
- 所得の確定前の寄付なので、最適な寄付の金額を予想で決める必要がある
- 自己負担金が発生するため、控除限度額を超えた寄附をすると損をする場合がある
ふるさと納税をした方が良い人と、しない方が良い人
した方がいい人
- ふるさと納税の控除限度額が7,000円以上となる人
- 特定の自治体を応援したい人
- 欲しい返礼品がある人
しない方がいい人
- ふるさと納税の控除限度額が7,000円未満となる人
- 余裕資金のない人
- 手続きが面倒だと感じる人
控除限度額の目安
ふるさと納税の控除限度額は、所得税率や住民税の所得割額を基に計算するため、不動産所得・事業所得・給与所得などの所得だけでなく、扶養控除などの所得控除の金額によっても変わってきます。
総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、給与収入と家族構成別の控除限度額の目安を紹介しています。こちらが参考になるのは給与所得者のみで、あくまで目安となっていますので注意しましょう。
また簡単な質問に回答すると、控除限度額をシミュレーションしてくれるふるさと納税サイトもありますので、活用してみるのもよいでしょう。こちらは不動産所得者、事業所得者などの個人事業主も利用できます。
手続きの流れ
給与所得者の人は、寄附先の自治体が5以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要となり、簡単にふるさと納税の手続きができます。
ただし、下記に該当する人はワンストップ特例制度は利用できないため、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例制度を利用する方法
1.ふるさと納税したい自治体を選ぶ
2.ふるさと納税を実施する
3.ふるさと納税を実施した自治体すべてへ「ワンストップ特例制度の申請書」を提出する(翌年1月10日まで)
4.翌年度分の住民税が控除される
確定申告する方法
1.ふるさと納税したい自治体を選ぶ
2.ふるさと納税を実施する
3.確定申告を実施する(翌年3月15日まで)
4.ふるさと納税した年分の所得税が控除・還付される
5.翌年分の住民税が控除される
手続きの違いによる、お住まいの市・県の税収への影響
ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税による控除は全額が「住民税」からの控除となります。一方で確定申告をした場合、控除は「所得税」から行われる部分と「住民税」から行われる部分に分かれることになります。
つまり、ワンストップ特例制度を使用すると、本来は国に納められる所得税から控除される金額が、市や県に納められる住民税から控除されるようになるため、お住まいの市・県の負担が大きくなります。
お住まいの市が地方交付税の「交付団体」の場合、ふるさと納税による減収額の75%が、地方交付税により国から補てんされます。一方で「不交付団体」となっている場合は、地方交付税による補てんがなく、ふるさと納税による市税の流出分は純粋な減収となります。
「自身が支払う税金は、できるだけ自身がお住まいの市や県のために役立ててほしい」という方は、ワンストップ特例制度ではなく確定申告を行った方が良いと言えるでしょう。
ふるさと納税はいつするのがいいか
ふるさと納税自体には、特に締め切りや期限がありませんが、限度額は年ごとになります。毎年1月1日から12月31日の1年間で行ったふるさと納税について、翌年に手続きをすることで税金の控除が受けられます。
ふるさと納税を年末にするメリットは、「寄付の限度額を計算しやすいこと」、これに尽きます。
一方で、ふるさと納税を年末にするデメリットもあります。忙しい年末につい手続きを失念してしまう可能性もありますし、ワンストップ特例制度の申請期限は翌年1月10日までのため、急いで申請する必要があります。また、まとめて何件もふるさと納税をすると、たくさんの返礼品が一度に届いてしまい、食料品などの返礼品を無駄にしてしまう恐れもあります。
まとめ
ふるさと納税は好きな自治体に寄付することで、所得税・住民税控除を受けつつ、返礼品をもらうことができる制度です。ただし、ふるさと納税には控除限度額があり、これを超えた寄付はすべて自己負担となります。
また、年収100万前後の非課税世帯は、ふるさと納税の控除限度額が0円です。つまり、ふるさと納税を利用しても全額自己負担となります。また、非課税世帯でなくても「控除限度額7,000円未満の年収世帯」は、ふるさと納税のメリットが享受できない可能性があります。ふるさと納税のシュミレーターを利用するなどして、控除限度額を把握しておくことが大切です。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、ふるさと納税の確定申告も行っていますので、ご自身での手続きに不安のある方はぜひお問い合わせください。