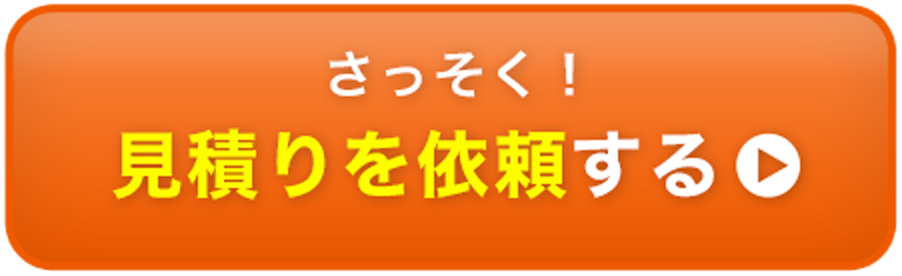少額減価償却資産の特例とは?消耗品費との違いを踏まえて節税方法を紹介

青色申告の特典である「少額減価償却資産の特例」とはどのようなものか?消耗品費や固定資産との違いを踏まえて解説していきます。
消耗品費とは
事業活動において使用する消耗品や消耗性のある資材に関連する支出のうち、購入価格が10万円未満か、使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のものを指します。
消耗品費と減価償却費
事業で使用する備品などで、その使用可能期間が1年以上のもので、10万円以上のものは、原則その資産の種類ごとに定められた耐用年数にわたって分割して経費化する「減価償却」という会計上のルールがあります。
具体的には、購入時には器具備品、車両運搬具など「資産」としておき、毎年度の決算でその年分の経費化金額を「減価償却費」として「費用」に振り替えるのです。
減価償却についての解説はこちらの記事もご覧ください。
白色申告者の取扱い
| 購入価格 | 処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額その年の経費に計上できる |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産にできる (3年間で均等償却する) |
| 20万円以上 | 固定資産に計上して減価償却しなければならない |
白色申告者は黒字(儲かった年)の年に10万未満の備品を買い込むと節税になります。注意点として、10万円未満の物であることに加え、同年中に備品の使用を開始する必要があります。未使用品はたとえ10万円未満の物であっても「貯蔵品」として資産計上し、使用を開始した年に経費化することになるためです。
また、取得価格が10万円以上20万円未満の固定資産を3年で均等償却する制度である「一括償却資産」として処理することもできます。例えば、18万円のパソコンを購入した場合は、毎年6万円ずつ減価償却することができます。
20万円以上の物を購入した場合は減価償却資産として、その資産ごとの耐用年数により減価償却をしなくてはいけません。
青色申告者の取扱いと少額減価償却資産の特例
| 購入価格 | 処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額その年の経費に計上できる |
| 10万円以上30万円未満 | 年間300万円までは全額その年の経費に計上できる ※10万円以上20万円未満であれば、一括償却資産(3年間で均等償却)も選択できる |
| 30万円以上 | 固定資産に計上して減価償却しなければならない |
青色申告者は黒字(儲かった年)の年に30万円未満の備品を買い込むと節税になります。青色申告者は、事業に関係する30万円未満の資産を購入した場合には、年間の合計購入金額が300万円になるまで、全額その年の経費にすることができます。よって、黒字の年には30万円未満の備品を買い込めば節税することができます。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。注意点としては、白色申告者の説明と同様に、同年中に備品の使用を開始する必要があります。
また特例を受けるための条件として、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載(摘要欄に「措法 28の2」と記載)して、明細を確定申告書に添付して提出する必要があります。そして、少額減価償却資産の取得価格の明細を保管しておかなければなりません。
金額の判定にあたって気を付けること
セットで使用する場合や付随費用がある場合
10万円未満、20万円未満、30万円未満と3つの「未満」がありますが、この〇万円未満の判定で気を付けなければいけないのが、セットで使用することが前提のものはセットの金額で判定するという点です。
例えば、応接セットのように椅子とテーブルがセットになっているものは1脚ごとで判定することはしません。単品でそれぞれ〇万円未満であってもセットで〇万円以上になっていれば、固定資産にしなければいけません。
また、その資産を実際に使用するまでの付随費用(運送費や設定費用、設置費用など)があれば、それらの費用も含めて判定しなければなりません。例えばエアコンを購入して設置してもらう場合は、設置の工賃も含んだ金額で判定することになります。
消費税について
| 税込場合をしている場合 | 税抜経理をしている場合 | 免税事業者 |
|---|---|---|
| 消費税込の総額 | 消費税を含まない金額 | 消費税込の総額 |
事業主が消費税の経理方法で税込経理・税抜経理のどちらを採用しているかによって変わります。税込経理の場合は税込の総額で、税抜経理の場合は消費税を含まない金額で判定します。免税事業者の場合は税込の総額で判断します。
一括償却資産と少額減価償却資産の違い
| 一括償却資産 | 少額減価償却資産 | |
|---|---|---|
| 利用できる者 | すべての企業、個人事業主が対象で、条件なし | 青色申告者が対象 |
| 対象になる固定資産 | 10万円以上20万円未満 | 10万円以上30万円未満 |
| 事業年度ごとの上限 | なし | 300万円まで |
| 償却資産税の対象となるか | ならない | なる ※課税標準額が150万円未満の場合は課税されない |
| 適用期限 | 恒久 | 2026年3月31日まで ※税制改正で延長される可能性あり |
| 税務上の償却方法 | 3年間で均等償却 | 取得価格の全額を損金に算入 |
一括償却資産には「償却資産税の課税対象とならない」という隠れたメリットがあります。一括償却資産は3年間で均等償却する、少額減価償却資産は購入した年に全額経費化できる、という取扱いの違いがありますが、最終的に購入金額の全額が経費になることは同じです。所得が毎年平準化されているような場合は、10万円以上20万円未満の資産には、あえて一括償却資産を選択して「償却資産税の課税対象とならない」メリットを取ることも考えられます。
まとめ
購入した備品などを安易に消耗品費などとして経費処理をしてしまうと、場合によっては資産計上が必要なものとして、税務調査で指摘を受けてしまう可能性があります。
また青色申告者は少額減価償却資産の特例を適用できますが、適用に当たっては慎重に金額判定をする必要があるほか、確定申告に必要事項を記載し明細書を保管するなど、一定のルールがあります。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、少額減価償却資産の特例の適用や償却資産税の申告代行なども行っていますので、ご自身での手続きに不安のある方はぜひお問い合わせください。