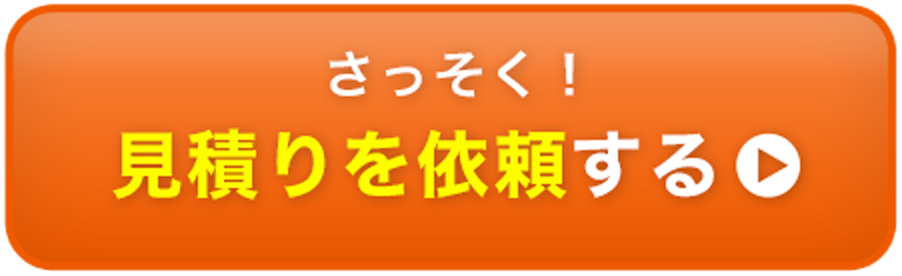税務調査とは?(1) 調査になりやすいケースや調査を受けないために気を付けることを紹介
税務調査とは何か、調査の種類や調査対象に選定されやすいケースを解説します。
税務調査とは
国税庁が管轄する税務署などによって、納税者が提出した確定申告書の申告内容や納税額に、問題が無いかどうかを確認するために行う調査です。
すべての事業者に対して行われるわけではありませんが、所得税の調査については、事業所得者や不動産所得者などの個人事業主だけでなく、副業を行っている会社員なども調査対象になっています。
税務調査の種類
税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類がありますので、それぞれ解説していきます。
強制調査
いわゆるマルサ(国税局査察部)の調査で、起訴されるような大がかりな脱税に対して行われるものです。マルサは裁判所の令状をとっていますので、この調査を断ったり逃れたりする術はありません。
しかし、強制調査は通常、目安として脱税額が1億円以上、少なくとも数千万円以上と疑われるようなところにしか行われおらず、対象となるのは全国で年間200件ほどです。
よって、一般の個人事業主や会社員が強制調査を受けることはまずないと言えます。
任意調査
納税者の任意で行われるもので、税務調査のほとんどがこの任意調査です。任意調査だからといって、納税者が調査をまったく断ってしまうようなことはできません。税務調査官には、税金に関してどのようなことでも質問したり、調べたりできる「質問検査権」という権利があります。この質問検査権は国税通則法で定められている調査官の権利であり、質問検査権に基づいた質問に応じなかったり、帳簿の提示や提出などに応じなかったりした場合は、罰則が規定されています。
そして納税者には、税務署が質問してきたときには、それに答えなければならない「受忍義務」があります。もし税務署の質問に虚偽の回答をしたり、知っていることを黙っていた場合には、加算税や延滞税などのペナルティの対象になってしまいます。
任意調査の「任意」とは、税務調査を受けなくてもよいという意味の任意ではなく、「令状をもった強制調査ではない、税務調査官の質問検査権に応じる形で進める調査」という意味での任意ということになります。
どんな人に税務調査が入るのか
提出された確定申告に不審な点があった場合に行う、という建前になっています。確定申告書になにかおかしな点が見つかったり、不正の情報が寄せられたりしたときに行われることになっています。
しかし、実際には提出された申告書を見ただけで不正を見抜くことは困難なこともあります。また不正の情報などもそうそう出回るものでもありませんので、必ずしも不正があることを前提として税務調査が行われる訳ではありません。どんな事業者にも税務調査が入る可能性があるとも言えます。
税務調査に選定されやすいケース
所得税の確定申告件数は毎年8万件~9万件と、膨大な数の申告書が提出されますので、そのすべてを調査するわけにはいきません。したがって、ある程度の基準に沿って調査対象の選定が行われています。税務調査に選定されやすいケースは、主に以下のようなものがあります。
まとめ
税務調査の種類と調査対象に選定されやすいケースを解説しました。税務調査を受けないために気を付けること、税務調査を受けることになった場合の対応、は次回の記事で解説します。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、信頼性の高い税理士署名の確定申告書を作成し、万一税務調査があった際には調査対応もお受けしています。ご自身でのお手続に不安のある方はぜひお問い合わせください。