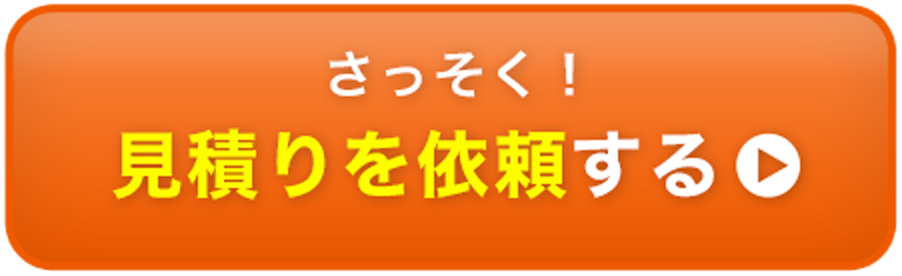小規模企業共済とは? 不動産オーナーも事業的規模であれば加入できる、有効な節税手段

小規模企業共済とはどのようなものか、加入資格や掛金について、加入のメリットについて解説していきます。
小規模企業共済とは
「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が小規模企業の傾斜に向けて運営している共済制度で、主に小規模な個人事業主や会社役員の退職金代わりに利用されている制度です。従業員が5人以下の個人事業主やフリーランサーが加入でき、低金利の貸付制度を利用することもできます。
「個人事業を廃業したとき」、「法人が解散したとき」、「役員を退任したとき」に、小規模企業共済制度に加入していると、「生活資金」、「退職金」、「事業資金」などを受け取ることができます。
メリットとデメリット
メリット
- 掛金が全額所得控除になる
- 掛金月額は増減可能
- 受取は一括・分割の選択可能
- 低金利の貸付制度を利用できる
- 共済金の受け取り時は退職金または年金の雑所得扱いとなり税金が安くなる
デメリット
- 12か月未満の掛け捨てリスク
- 加入期間20年未満は元本割れ
- 受取時には課税される
- 預貯金と違って自由に引き出すことができない(※)
- 事業を廃業しなくても解約できるが、その場合は給付金が若干少なくなる。
(※)経営セーフティ共済のように、40か月を過ぎて解約をすると解約返戻金が満額受け取れるという仕組みはありません。
加入資格
加入できる要件
- 従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主や、中小企業の経営者、役員
- 税務署に開業届を提出して、事業所得を得ていることにより確定申告をしている方
- 会社との間で雇用関係が生じていない方(給与所得を得ていない)
- 固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である方
- 社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる方(事務所を有している、常時事業に従事している等)
「事業的規模」の判定については、以下の記事もご覧ください。
加入できない要件
- 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問そのほか実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
- 得率行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下、中退共等)の被共済者
- 生命保険外務員
- 配偶者等の専従者・従業員(ただし、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」として加入できます)
- 小規模企業共済に該当する個人事業主であるほかに、小規模企業共済に該当しない事業の兼業や役員をしている方
- 学業を本業とする全日制高校生等
掛金
月に1,000円から7万円までの範囲内で、500円単位で自由に選べます。加入後、掛け金の増額・減額ができますが、減額の場合は一定の要件を満たすことが必要です。
また、業績が思わしくなくて掛金を納めることができない場合は「掛け止め」もできます。
低金利の貸付制度について
貸付の種類
- 一般貸付
- 緊急経営安定貸付
- 傷病災害時貸付
- 福祉対応貸付
- 創業転業事、新規事業展開等貸付
- 事業承継貸付
- 廃業準備貸付
貸付限度額
掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入をすることができます。
共済金の種類と受け取れる共済金
事業を廃業したとき、会社の場合は役員を退任したとき、などに受取ことができます。共済金は税法上の扱いは、共済金などの種類や受け取り方年齢などによって異なります。共済金などの種類は請求事由によって以下の4種類に分けられます。
| 共済金等の種類 | 個人事業主 |
|---|---|
| 共済金A | ・個人事業を廃業した場合 ・共済契約者の方が亡くなられた場合 |
| 共済金B | ・老齢給付 ※65歳以上で180か月以上掛金を納付された場合 |
| 準共済金 | ・個人事業を法人成りして加入資格がなくなり、解約した場合 |
| 解約手当金 | ・任意解約 ・機構解約 ※掛金を12か月以上滞納した場合 ・法人成りして加入資格がなくならなかったが、解約した場合 |
小規模企業共済で受け取れる共済金
例)掛金月額1万円の場合
| 掛金納付年数 / 掛金額合計 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 / 60万円 | 62万1,400円 | 61万4,600円 | 60万円 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80~120%相当額を支給 |
| 10年 / 120万円 | 129万600円 | 126万800円 | 120万円 | |
| 15年 / 180万円 | 201万1,000円 | 194万400円 | 180万円 | |
| 20年 / 240万円 | 278万6,400円 | 265万8,800円 | 241万9,500円 | |
| 30年 / 360万円 | 434万8,000円 | 421万1,800円 | 383万2,740円 |
加入の申込先、問い合わせ先
金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会など
必要書類
- 契約申込書
- 預金口座振替申出書
- 確定申告書の控え(個人事業主の場合)
まとめ
小規模企業共済は、毎月お金を積み立てて、自分が引退するときや会社を廃業するときに、通常の預金利子よりも有利な利率で共済金を受け取ることができます。またセーフティ共済と同様に、掛け金の全額を所得から控除できます。
前納することができる上に、1年以内分の前納額は支払った年に全額を所得から控除できるので、年末に月々7万円の掛金で加入し、1年分前納すれば、年末に84万円を所得から一気に控除できます。
共済金を受け取った場合は、税法上、退職金または公的年金と同じ扱いとなるため、税負担が抑えられます。
フラッグシップ税理士法人「不動産オーナーのための確定申告代行サービス」では、小規模企業共済の加入に関するアドバイスも行っていますので、節税方法として検討されている方はぜひお問い合わせください。